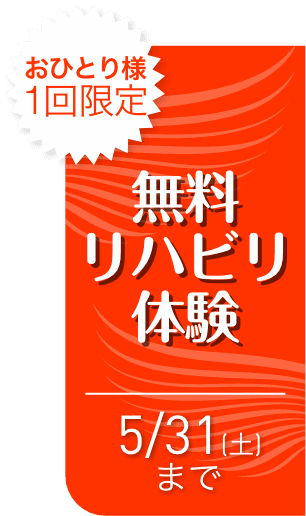こんにちは!京都にある自費リハビリセンターを運営しています。
センター長の米田です。
今日は足部のすくみ足の原因について語っていきます。
1.はじめに
すくみ足は、パーキンソン病における特有の歩行障害であり、歩き始めや方向転換時に足が床にくっついて動き出せなくなる症状です。この現象は、以下のような複数の要因によって引き起こされます。
2.すくみ足の主な原因
神経伝達の異常: パーキンソン病では、脳内のドーパミンが減少します。ドーパミンは運動をスムーズに行うための指令を出す役割を果たしており、その減少により運動の開始や切り替えが難しくなります。
筋肉のこわばり: パーキンソン病の患者は、筋肉の固縮が見られることが多く、これが足の動きを制限します。特に、下肢の主働筋と拮抗筋の相反性の障害が影響を及ぼすと考えられています。
近年の研究ではすくみ足の要因として脊柱起立筋の弛緩が出来ない事が挙げられます。
環境や心理的な要因: すくみ足は、狭い場所を通るときや目標物に近づくとき、または精神的な緊張があるときに特に起こりやすいです。これらの状況では、身体が動きにくくなることがあります。
内的リズム障害: 近年の研究では、すくみ足は単なる筋力低下やバランスの問題だけでなく、脳内のリズム生成の障害にも起因していることが示されています。
3.改善方法
以下に、すくみ足を改善するための具体的な方法をいくつか紹介します。
リズムを意識した歩行
メトロノームや音楽を使って、一定のリズムに合わせて歩く練習が効果的です。リズムを意識することで、足が出やすくなります。例えば、「1、2、1、2」と心の中でリズムを刻むだけでも効果があります。視覚的な手がかりを利用
床にテープや線を引いて、その上を歩く練習をすることで、視覚的に足を出す位置を調整します。目の前に線があるとイメージするだけでも、足が出やすくなることがあります。方向転換のトレーニング
歩行時に大きな動作を意識する練習を行います。方向を変える際には、歩幅を大きくしながら円を描くように回ることが重要です。小さな動きではなく、大きくゆったりとした動作を心がけましょう。筋力強化トレーニング
下半身の筋力を強化することで、歩行の安定性が向上します。椅子に座った状態から立ち上がる練習や、ゆっくりと座る練習を繰り返すことが推奨されます。ストレッチと柔軟性の維持
背筋を伸ばすストレッチや体をひねるストレッチを行い、柔軟性を保つことも重要です。これにより、筋肉のこわばりを軽減し、歩行がスムーズになります。心理的な要因への配慮
歩行時のプレッシャーを軽減し、リラックスした状態で歩くことが大切です。心の緊張をほぐすことで、すくみ足の症状が改善されることがあります。
これらの方法を日常生活に取り入れることで、すくみ足の改善が期待できます。リハビリやトレーニングを継続することが、歩行の改善に繋がります。
4.まとめ
すくみ足は、パーキンソン病における複雑な症状であり、神経伝達の異常、筋肉のこわばり、環境要因、心理的要因、さらには脳内のリズム障害が相互に作用して引き起こされます。これらの要因を理解することで、適切なリハビリテーションや対策を講じることが可能になります。
京都のエール神経リハビリセンターでは、病気によって今後の生活が不安なあなたに寄り添います。オーダーメイドで適格な運動プランの提案や訓練を提供!
ご利用者様の身体状況に合わせてリハビリを進めていきます。
エール神経リハビリセンターの動画はこちら↓↓↓
経験豊富な理学療法士・作業療法士がチームを組みご利用者様の思いを実現できるよう最善を尽くします。ご興味があれば体験に来ていただけると嬉しいです。
また、脳卒中後遺症による麻痺だけではなく、パーキンソン病などの神経性障害や、変形性膝関節症、脊柱管狭窄症などの運動器疾患、慢性疼痛など様々なお身体の悩みに対しても対応させて頂いております。
現在、エール神経リハビリセンター伏見ではリハビリ体験を実施しております。
リハビリ体験はこちら↓
特別リハビリ体験のご案内 | エール神経リハビリセンター 伏見 (aile-reha.com)
LINEでもお気軽にお問合せ下さい↓
https://page.line.me/993lksul?openQrModal=true
お電話でのお問い合わせも対応しております。
お気軽にお問い合わせください。